現在年収の壁103万円をめぐる議論が政府与野党で議論されています
物価が上がった分だけ基礎控除額を引き上げなければ国民の手取りが減ってしまう事はごく普通の現象であるわけです(*´ω`*)
財源の問題?
社会保障サービスが維持できない?
政府歳入額は過去最高を記録している?
・
・
・
103万円の壁を撤廃出来る理由、出来ない理由、色々挙げたら切りがないけど流石に政府は税金を取り過ぎではと思われる方は少なくないはず!
筆者もその一人として今後の増税予定、検討されている増税案について調べてみました
増税といっても税金と社会保険料は別物のでは?
とマネーリテラシーが高い方は突っ込みたくなる部分もあると思いますが今回は税金と社会保険料も含めて今後徴収が検討されている(確定も含む)増税案をリストアップしましたので是非ご覧ください

検討されている増税案(社会保険も含む)
以下が今後増税、徴収予定の社会保険制度です
- 子ども・子育て支援金制度(通称:独身税?)
- 金融所得課税
- 通勤手当課税
- 走行距離税
子ども・子育て支援金制度(通称:独身税?)
2026年4月から開始予定とされているのが「子ども・子育て支援金制度」です
社会保険料からの徴収となり徴収目的としては社会全体でこども・子育て世帯を応援していくために児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部とされています(子ども家庭庁ホームページ記載の文言)
子供がいるかいないか、結婚しているいないかどうかに関わらず社会保険料に上乗せされます
世間では報道やSNSの情報で独身や子供がいない人にはメリットがないとして独身税と揶揄されていましたが社会保険制度に加入しているすべての人から徴収されます
加入者1人あたりの平均月額は2026年度は250円、2027年度は350円、2028年度は450円と試算されており加入している保険制度や収入によって数十円~数百円の差が出るようです
社会保険料は労使折半なので雇用主である企業も加入者と同額が徴収されます(加入者が250円負担なら企業も250円負担)
子ども・子育て支援金制度について筆者が思う事
子供の出生率は今後の日本の成長に様々な面で影響を及ぼしますわけですがその出生率は2016年から連続で減少し2023年に過去最低を記録したそうです
国を挙げて少子化対策に早急に手を打たなくてはならない状況であるのは分かるのですが保険料を支払う筆者としては下記の理由から腑に落ちない点があります
この制度に伴う政府の歳入額は2026年が約6,000億円程度、2027年度が約8,000億円程度、2028年度が約1兆円程度になると試算されています
一方、子ども家庭庁の予算は7兆円だそうでさらに1兆円の追加予算を申し出ているそうです
7兆円÷1401万人(2024年 15歳未満の子供の数)=496万円
子ども家庭庁を失くせば子供一人当たり年間496万円ばら撒ける計算ですよね!!!
496万円は日本人年収の中央値より高い額です
結論、筆者としては問答無用で取りすぎだと思います

金融所得課税
現在の金融所得課税は一律20%(所得税15%、住人税5%)となっておりこれを税率30%にしてはどうかと議論されています
昨今、NISAやiDeCoなど政府が投資による資産形成を推し進めている中、逆行する政策のよう思えますがこの政策の目的は所得格差の是正の為、高所得者を中心に増税しようという内容のようです
日本では高所得者ほど金融所得の割合が多い傾向にあります
給与や事業などの所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度ですが金融所得課税はどれだけ稼いでもNISAなどの非課税枠を除いて税率は20%とのままとなります
所得税が累進課税で金融所得課税が20%の場合、全所得の合計が1億円以上となると税負担率が緩やかに減少するため低所得者との税負担率に不公平が生じているのが現状です
金融所得課税について筆者が思う事
結論、筆者としては理に適っていると思うので賛成派です
政府が推し進めている新NISAの非課税枠は年間360万円で総額1800万円ですのでこれからこつこつ投資を始めようとする人には害はありません
むしろ年間360万円もの大金を投資に回せる余裕のある国民は殆どいないと思うので低所得者や中間層にとっては改悪というわけでは無いように思えるからです
一方、高所得者にとっては改悪なので株式市場から撤退したりお金持ちが日本から世界に出て行くのではないかと懸念がされているようですが考えすぎではないかと思います
なぜならお金持ちは複利の重要性を知っています
複利とは利息に対してさらに利息が付くという考え方ですがこれは投資の世界のみならず稼ぐという行為の本質的なところに当たります
お金持ちは金融所得での複利が低くなれば別の稼ぐ柱を作りそれを複利と捉えて稼ぐすべを知っているはずです
これは洩れなくお金持ちが持ち合わせている概念です
日本における高所得者の割合が多いわけでは無いので増収分としては僅かな額ではないかという批判もあるようですが僅かな額でも低所得者の為に使われる税金なのであれば筆者は納得できる増税案ではないかと考えます
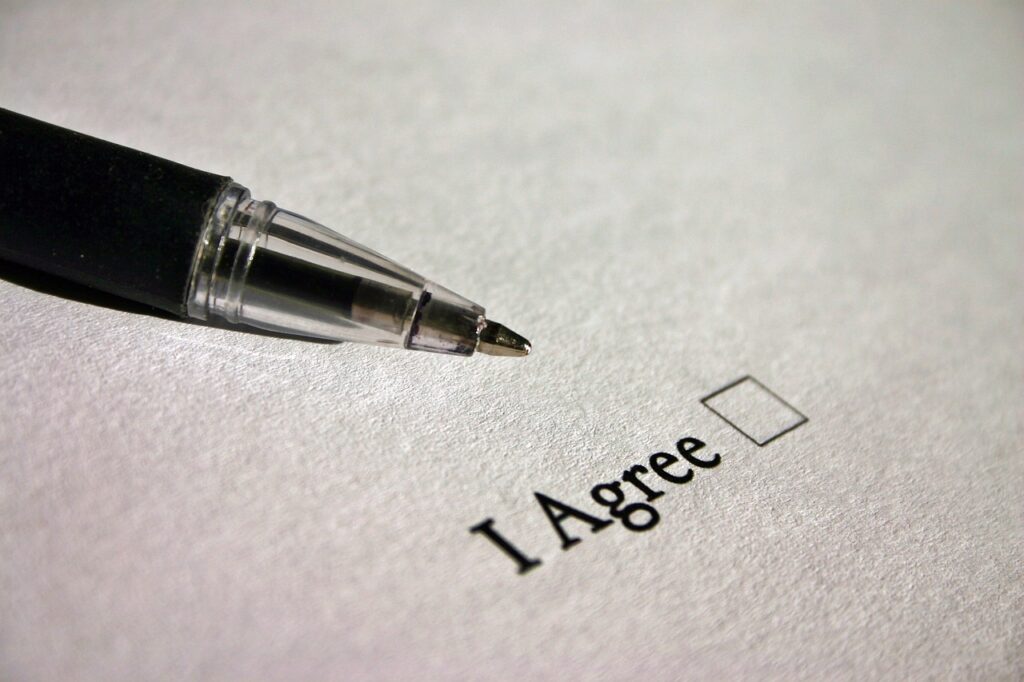
通勤手当課税
雇用主に雇われている人が仕事の為に出勤する際、雇用主側から通期手当が支給されます
法律では15万円を限度に自宅から勤務地までの距離や交通手段に応じて通勤手当が支給されていますがこの非課税枠廃止して給与と同様に通勤手当に課税する事が検討されていると噂されています
現在、国会では通勤手当に課税する事を目的とした議論がなされているわけではありません
しかしながら政府税制調査会が「現行の通勤手当の非課税枠は妥当であるが注意深く検討する必要がある」とコメントしている事から増税のターゲットにされているとみて良いでしょう
通勤手当課税について筆者が思う事
現時点では政府税制調査会も通勤手当の非課税枠について妥当と考えているわけなので特に何の心配もいらないと思います。
というより撤廃する事を進めているわけではないのでコメントしようがありません(>_<)
ただ非課税枠を撤廃する事を推し進めるのであれば撤廃するだけの妥当性を示すべきだと筆者は考えます(というか当たり前です!!)
走行距離税
自動車の使用目的を問わず実際に走行した距離に応じて課税する事が検討されています
目的としては電気自動車の普及などによってガソリン税から得られる税金の減少を押さえたいという意図があるようです
走行距離税も通勤手当課税と同じく詳しい議論は始まっておらず導入の予定もないようです
しかし令和7年度税制改正大綱で自民・公明の与党は公平・中立・簡素な課税のあり方について中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行う必要があると記しています
走行距離税について筆者が思う事
もし走行距離に応じて課税されるとすると走行距離が多い人ほど税金が高くなるわけです
走行距離税を押さえる為に自動車利用者の移動範囲が狭くなると経済活動は落ち込みさらなる税収落ち込みに繋がる事は明白です
また物流コストがあがるので物の値段はすべてのジャンルで上がる事が容易に想像できますよね
現在50年前から続くガソリン暫定税率も本来の期限から延長を繰り返しておりガソリン税との2重課税になっているという指摘に対して明確な回答がないままです
筆者は到底、「はい、そうですか」と言える状況にないと思います

この記事を書いて思う事
増税と言うと聞こえが悪いかもしれませんが税金は国の貴重なの財源であり一部の人を豊かにする為のお金ではありません
その税の使い道が不明瞭であったり妥当性がないと国民から不満が生まれるのは当然です
独身税などという言葉が独り歩きしてしまうのも国民の税に対する不満の表れだと感じました
とはいえ日本の高齢化社会が進み現役世代が減少している中で税収の減少に拍車が掛かっているのも事実です
取れるところからは取り、失くせるものは失くすという基本的なバランスに捻じれが生じた結果が今の日本の姿なのではないでしょうか
今回は予定されている、もしくは検討されている増税案について記事にしました
今までのブログのテイストと違いかなり小難しい内容になってしまったので読みにくかったのではないかと少し反省しております
今後も私の目線で問題提起する記事は書いていこうと思いますので興味のある方は読んで頂けるとうれしいです
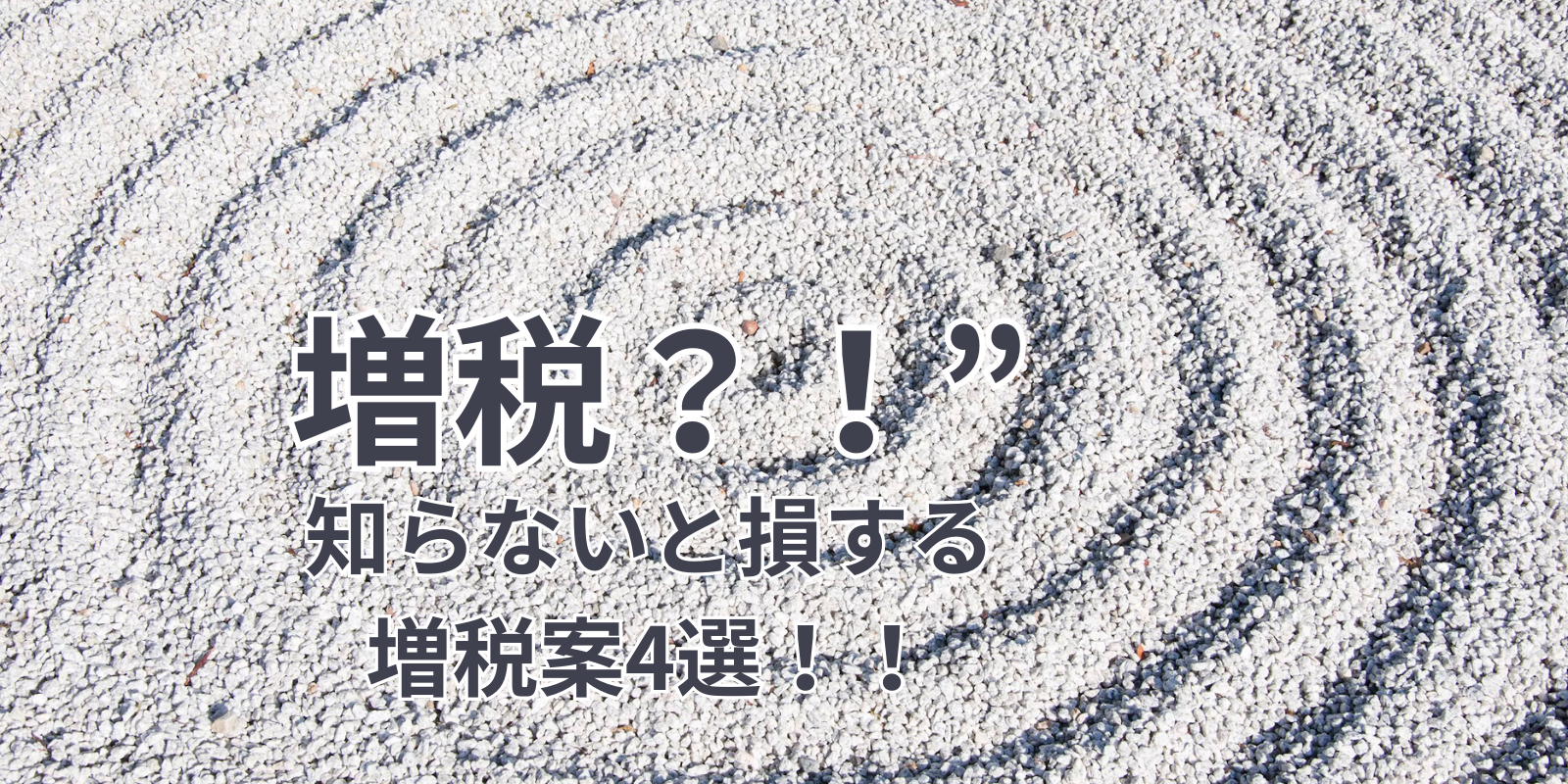


コメント